大佐認定までされたアニ小説の名作。
濡れ場までちょっと長いけど、そこが濡れ場を盛り上げる!
■所要時間:26分 ■本文:18レス
アブっぽいやつ寄ってく?
「【進撃の巨人エロSS】エレンに対人格闘術を教えていたアニが、今までの授業料としてエレンに要求したものは・・・」開始
アニ×エレンのうぷろだのアドレスを貼りはしましたが、待ちが多く落としづらい方もいるようで心苦しく思っていました。
また、せっかくの進撃エロパロスレにSSが少ないのも寂しく思っていました。
規制やらリセットやらも片付き投下できるようになりましたので、長いですが改めて本文を投下させていただきます。
にぎやかしになれば幸いです。
また、うっかり誤字や脱字、勘違いや推敲漏れを数箇所修正してありますが、うぷろだに上げたものとお話に違いはありません。
初見の方へ
投下内容はアニ×エレンのエロパロSSです。
45KBくらいと少々長めで、濡れ場は後半となっております。
原作での時間軸的には、原作一巻で訓練兵トップ10が発表される10日ていど前の時期に設定しています。
では次レスよりどうぞ。
タイトル 『獅子ノ乙女宵闇情歌』(ししのおとめよやみのこいうた)
「遠慮なんてしなくていいって」
そんな台詞が乾いた空気を揺らすのはもう何度目だったか。喋った方も、聞かされた方も、そんな瑣末な事はもちろんいちいち覚えていない。
今日もそんなおさだまりの一言のあと、向かい合った少年少女のあいだの空気が一瞬にこわばる。
新兵訓練所の屋外、対人格闘術の訓練の一齣だ。
いつものように――少年が夢中で突進する。その先の相手、細身の少女をめがけて踏み込みながら、振りかぶった拳を突き込んだ。
その刹那だった。鞭のようにしなった少女の手がその拳をはじき、手首を巻くように掴んでいた。
同時に少年の内懐に入りざま肩に担ぎ上げ、その身を宙に跳ね上げる。
次の瞬間、少年は息をつく暇もなく背中から土の上に逆落しに叩きつけられていた。
「うごぁっ!」
少年の肺の中の空気が呻きと共に吐き出される僅かの時間に、少年の上に乗った少女の膝と襟を持った外腕がそれぞれ腹と喉を押さえて動きを制していた。
いつの間に抜刀したのか、一方の手に握られた木製の短刀が肋骨の隙間を通るように正確に心臓に擬せられている。
抵抗不可能――。まさに少年の生死は完璧に少女に握られた状態になっていた。
「いてて…クソッ…!まいったまいった」
たまらず少年が声を上げた。
黒髪の、少し気性の荒さを感じさせる精悍な顔立ちだった。痛い目に遭いながらも眼がギラギラと光っている。
その少年、エレン・イェーガーは少々悔しそうに少女を押しのけ、起き上がる。
「この技の要諦は。いいか?エレン」
エレンから離れた少女が静かに口を開いた。その声音は静かだったがどことなく威がこもっている。
青い湖水のような双眸をエレンに向け、金髪の少女――アニ・レオンハートは淡々と続ける。
獅子の心胆、をその名に持つ彼女の口調は事務的で冷静だった。
「奇襲を捌いて投げるだけで終わりじゃあない。投げたあと、反撃を許さず止めを刺す事にある。
本当は脳天から落とすんだ。ナイフで一突きはダメ押し…いいか?」
「一回でわかるかよ…」
唇を尖らせたエレンは、しかしどこか嬉しそうだった。
「ま、しっかし毎度すげえ技術だよな。ちゃっちゃとモノにして見せるぜ」
「フン…じゃ、ライナーとやってみな」
「ああ。自分よりでかいヤツのほうが練習にゃいいからな」
エレンはそう言ってぴょこんと立ち上がると、傍らで一連の組み手を見ていた巨漢の方に寄っていった。
その背を見送ったアニは膝の草を払って立ち上がり、そして視線をめぐらせた。
周囲は同じように取っ組み合う同年代の少年少女の怒号や拳足の応酬でたいそうな熱気だった。
もっとも、今のエレンを制したアニの動きほど水際立ったキレを見せているのはほんの数人ほどだ。
だらだらと適当に流している者や、ふざけているのか滑稽な構えでダンスを演じている者が大半だった。
時おり、眼を光らせながらその間を見て回る教官の叱声が飛んでいる。
それはいつもと変わらない光景――。
ここ新兵訓練所に入所した時から、この対人格闘術の訓練の時間はどこか怠惰の空気が漂っている。
それもそのはず。
対人格闘術など、人類を圧倒的に凌駕する体格をもつ人類の天敵、『巨人』に対しては何の役にも立たないのだから。
この世界のあらゆる戦術理論、軍組織の編成と兵士養成のカリキュラムは、ほとんど全てが巨人に対抗する、その一点を目的としている。
ゆえに兵士は巨人を殺す唯一の戦闘術――立体機動装置と双刀による三次元的高速機動白兵戦技、これを最も重要な技術として訓練される。
対人格闘などおまけにすぎない。実際、訓練兵の能力評価項目でも対人格闘術の重要度は低い――点数にならないのだ。
そんな技に秀でるアニも、熱心に習得に励むエレンも、要するに異端者と言って差し支えないのだった。
「…すげえ技術、か…」
彼女が格闘技術に秀でているのは、ものごころついた時から父に叩き込まれた、ただそれだけが理由だ。
巨人が天敵として存在するのに、こんな技術など何の意味も無いことはおさな心に分かりきっていたが、それでもアニは父親に逆らえなかった。
言われるままミットに蹴りを叩きつけ、突きをぶち込み、巌のような体躯の父と取っ組み合った。
アニの体格が小柄なのは、幼時からあまりに過酷な運動を強いられたからかもしれない。
そんな過酷な時間と経験を経てアニの中にはその無意味な技術が骨の髄まで身についていた。
格闘技術とは要するに人体破壊の理論だ。整然と体系化された技術は習得過程で学ぶ者の思考方法の形成や性格に影響を与えずにはおかない。
アニは合理的で理論的な思考を身につけるとともに、無意味さへの不満や父親へ反抗できなかった自分への嫌悪などを同時に抱え込んで成長してしまった。
澱のように堆積したそれはアニの心を重くさせ、口を閉ざさせ、他者との協調性を乏しくさせていた。
ところが。
アニの唇がわずかにゆがむ。
もう結構経ったが、どのくらい前だったか―?
『教えてやってもいいけど?』『遠慮なんてしなくていいって』なんて、どうしてそんな台詞がこの自分の口から出たものだろう?
そんな台詞を言ってしまった結果として、自分はエレン・イェーガーというあの必死な目をした男にこの技術を教えている。
本当に、どういうわけなのやら…自分でもわけがわからない。
「おい、どうだ?アニ!」
その声でアニは我に返った。
見ると芝生の上で汗みずくの男ふたりがこちらを見上げている。
エレンがライナーの喉を押さえ、膝を鳩尾にのせていた。草やら土が所々に張り付いており、どうやらお互い何べんか反復していた様子だ。
一見して先ほどアニがエレンに示した形になっているようだったが――。
「は…」
アニは小馬鹿にしたように鼻を鳴らした。いつもの台詞が口をついて出た。
「全然駄目。まったくなっていない」
そして物覚えの良いとは言えない弟子?たちの方に踏み出してゆく。
――自分は今、笑っているのだろうか。
アニはそんな事を思っていた。
この訓練所には食事と同期の仲間たちとの会話以外に娯楽など無きに等しいのだから無理もない。
みな制服を脱いだ部屋着でテーブルでくつろいでいる。
もっとも支給される食事自体はたいしたものではない。パンと、豆や野菜が入ったスープ程度のものだった。
それでも兵士は食事だけは保証されているというのは人類の有史以来の不文律と言えようか。
アニは隅のテーブルで、周りの喧騒を少々うざったく思いながらパンをちぎっていた。
固めのパンをスープに少し浸して口に運んでいると、向かいに座ったおさげの少女が話しかけてきた。
「アニ、少し変わったね」
「…何?急に」
ミーナ・カロライナだった。豊かな黒髪を左右でまとめている。あまり他者に関わらないアニの数少ない話し相手だった。
「最初の頃、怖い感じだったよ、アニは。でも最近はちょっとだけ」
「ちょっとだけ…何?」
とげとげしいアニの反応にもミーナは慣れているのか、あまり意に介さない。
「本当にちょっとだけ、カドが取れた感じがする」
「…っ」
その返答はアニには、パンを吹き出しそうになる程度には意外だった。
アニは他者に無頓着なせいかその他者からどう見られているか意識しない。
ところがやはり他者はこちらを観察していて、そして親しければ会話の端にその変化をこのように指摘してくるものなのだ。
それは彼女が過去において持たなかった友人関係というものの端緒なのだが、そんな心の襞に疎い(というか注意を向けようとしなかった)
アニには新鮮なおどろきだった。
「私が…変わった?」
「うん。だいいち、前は気安くこんなこと言えなかったと思う」
どうして?どこが?どんな風に?
アニの中にはそんな疑問が浮かんでは消えたが、言葉にならない。
会話の成立が困難になりかけたとき、向かい合う少女たちのテーブルに、どん、と音がなった。
エレン・イェーガーの、手をついた音だった。
「アニ、ちょっといいか?」
そしていつも真顔だ。彼の目はまっすぐアニに据えられている。
「昼間の技とは別に、蹴り技の事なんだが」
アニはつい、その視線を受けてたってしまう――というより、なぜか彼女はエレンを無碍にはできない。あらわした態度はそれとは真逆だったが―。
「めんどくさい…」
「前聞いた体重を乗せるとか、膝のスナップとか…わからんところが山積みなんだよ」
「また課外授業?たいしたやる気ね」
「評価試験だって近いだろ?ちゃんとやることやっとかないとな」
訓練兵たちはいまや訓練課程の終了を間近に控えている。その最後に、各科目の試験が待っている。
ただ、エレンは試験に限らず技術的なことで疑問があると、すぐにその技術に長けた者に質問し指導を求めることがしばしばだった。
それは立体機動も座学も対人格闘も例外はない。彼の兵士としての向上心は半端なものではなかった――そら恐ろしいほどに。
直接の理由を彼は滅多に語らないが、同期の訓練兵たちはなんとなく察してはいた。
ただ、ミカサにだけはそんな相談を持ちかけないところに彼の複雑な心境を読み取れるかも知れない。
もちろんそれはアニには関係の無いことだったが。
ともあれ、エレンはうざったげなアニの態度に少し鼻白んだようだ。
「なんだよ、遠慮なんてしなくていいんだろ?」
「…確かに、そうは言ったけど」
「えっと、エレンいいの?ミカサがこっち見てるよ?ちょっと怖い顔してるよ?」
すかさずミーナのちゃちゃが入る。
確かに、離れたテーブルに座すミカサ・アッカーマンの視線が、矢のようにこちらに注がれていた。その眼はエレンの唇と、アニとミーナの表情を捉えている。
壁の内側の人類とは人種の違う「東洋人」の血を引くミカサの表情は全般的に変化に乏しい。
真っ黒なハイライトのない瞳が何とも言えぬ威圧感を放っている。いや、はっきり言うなら怖い。
唇の動きからエレンが何を言っているか読み取ってさえいるかも知れない、ミーナにはそんな疑念すら浮かんだ。
あの天才肌の少女が幼なじみのエレンに向けるある一種狂おしいほど逸脱した強い想いは、今期の訓練兵たちにはおおむね共通認識となっている。
エレンはそんな認識からの冷やかしに、当たり前のように反発した。
「なんであいつが出てくんだよ!俺は必要だから言ってるんだ」
「つまりアニが必要ってことぉ?ミカサよりもぉ?」
必要以上にムキになるオトコノコなど、年頃の少女にとってはいいおもちゃだ。ミーナはにやにやしながら突っ込んだ。
「…引っ込んでてくれよ、頼むから」
しかめっ面で歯をむき出すエレンの貌は、アニには他人事ではない。
自分に話が回ってくる可能性を嗅ぎとったアニは、さっさと会話を終わらせることにした。
「わかった、エレン。ミットを持って行くよ、それでいいんだろ?」
「ああ。すまねえな、アニ。場所はいつもんとこで頼む」
「アニがちょっと丸くなったの、…エレンのせいだったりする?」
真顔でアニに質問した。少女特有の論理飛躍は、しかし合理的なアニには不意打ちだ。
「…っ?!」
アニはたまらず含んだスープをひとしずく吹きこぼしてしまう。そんな反応はミーナには満足なものだったようだ。
「ま、理由はどうあれ、必要とされるって気持ちがいいもんね。それとも…」
下目遣いに、口元を拭うアニの眼を覗き込む。
「ドキドキしちゃってるとか?」
どん!今度はアニがテーブルを叩いていた。顔をそらしながら立ち上がっている。
「…!…どうでもいい…!」
アニはそれだけ言うと、スープもパンも残したまま足早に席を立ってしまった。
「あー…怒っちゃったー…。」
――こういう会話、慣れてないんだろうな、やっぱり。
ミーナに苦笑がこぼれる。
年頃の少女たちなら半ば必然的に話題とするであろう、ちょっと気になる男の子の話。それに関する冗談、雑談、ホンネと建前。
アニとはやはり、そんなおしゃべりはまだ無理のようだった。
――でもアニはそんなところが可愛いんだけど。
ミーナはそんなことを思いながら、友人の残り物と食器を片付け始めた。
さて、その皿に残ったスープとパンのかけらにはミカサとは別種の、さらに怖い視線が注がれていたのだが――その後の顛末は別の物語である。
兵舎の裏手、倉庫の脇はちょうどいい広さの空地になっていた。月のあかりがあたりを陰翳濃く塗り分けている。
ここは教官たちのいる建家からも遠く、音を立てても聞き取られにくい。
要するに、エレンの昼間の訓練の復習の場としては格好の立地となっていたのだった。
「しぃっ!」
鋭い呼気のあとに鈍い重い音があがる。
アニの外腿に携えた革のミットに、エレンが蹴りを叩きつけていた。すでに結構な本数をこなしたのか、エレンの額に汗が光っている。
おたがい、上着にズボンと革靴の部屋着だった。
「…力みすぎ。動作の起こりでは力を抜いて。入れるのはインパクトの一瞬だけ」
細かい注意がアニから飛ぶ。応えるようにエレンが蹴りを返す。習ったとおり蹴り足を変え、左右の構えを変え、蹴りの質を変える。
アニの教えでは――それは彼女の父が伝承してきた教えだったが――あまり高い蹴りを打たない。
敵手にキャッチされてしまったら金的を蹴り上げられたり軸足を捌かれてテイクダウンされてしまうので、
中段下段の前蹴りや回し蹴りが中心だ。狙うのは肝臓や水月、金的、膝関節などだ。
アニとその父が修めている技術はかつて人類社会で競技化され高度化細分化した格闘技術よりはるかに荒っぽい。
失伝によりもはや再現不可能な技術や理合も多いのだ。しかし制圧と殺傷を目的とした即効的で合理的な面を残したものと言えた。
エレンも例外ではなく、熱くなった身体の沸くまま、アニに蹴り以外の技もついでに教えてくれと言い出していた。
いつのまにやら、脛や膝を蹴ってからそのまま足の甲を踏みつけ、手技や組みにゆく技術の稽古になっていた。
アニはミットを放り出し、向かい合う受けに回ったエレンに手本を示してゆく。
間合、お互いの体格、どの足でどの足を踏んだか、などの状況によって様々に展開されるアニの技は多彩なものだった。
指を弾くように使った目打ち。平拳や親指を立てての喉突き。顎への肘打ちや掌打。頸動脈への手刀。眼を塞ぐような平手のフェイントからの様々な変化――。
ひとつの動作を起点に、アニの細身のしなやかな身体は受け手のエレンを翻弄するように自在に踊る。
――まただ。なぜ自分はこんな事をしているのか。適当に蹴らせて、切り上げればよかったのに――
アニは拳足を鞭のようにうねらせながら考えていた。思考とは別に動く身体はエレンに技をかけては離れる事を繰り返している。
だが胸のうちにはさっきのミーナの言葉がずっとひっかかっていた。
『必要とされるって気持ちがいいもんね』
――無意味な、少なくとも私は無意味と思っている、役に立たない技術を。エレンは。
この男の過去はライナーからうっすらと聞いた。エレンは巨人に復讐するために兵士になった。なろうとしている。
いや。その精神はすでに筋金の入った兵士、戦士なのだ。
だから、エレンはその責務としてこんな無意味な技術も欲しがるんだ。
エレンが私に関わるのは、私が技術を持っているから、だ――
だがアニはそんな自らに言い聞かせるような思考の根本原因には意識を向けなかった。
合理的な彼女は心の何処かでわかっていたのだ。
…リスクは回避する、と。
だが、現実にはそんな理屈と行動は乖離し、アニはエレンの稽古に付き合ってしまっている。いまだ未熟な若年ゆえに。
「ちょ、ちょっと待てアニ!そんないっぱい覚えられないだろうが!」
「…ん…ああ」
言われてアニは動きを止めた。
白い肌はさすがに上気していた。頬がほんのり紅い。ひとすじ張り付いた汗に濡れた髪をかきあげた。
ぞくり。
アニの何気ない動作に、エレンは背筋に何かが走ったのを自覚していた。それがなんなのかは――彼にはわからない。
型を示しながら動いているうちに――いつの間にか、汗とは別な何かをアニはまとっていた。その何かが、エレンの胸に靄のようにかかっている。
エレンはそれが本能的に怖くなって、
「アニ、今日はそろそ…」
と言いかけた。が――。アニの声がかぶさった。
「…じゃあ最後に、…組み手、でも…するか?」
アニの青い双眸がエレンに向けられている。月のあかりが微かに宿って、潤んだようにおぼろに光っていた。
「い、いや…」
いつもは明快なはずのエレンのたどたどしい声が闇をさまよっている。
そんな声が、アニの中の何かに、こつりと当たる。
アニの内側をぐるぐると往来していたわけの分からない思考が、ふっと止まった。
唇が、動きそうになった。瞬間、アニは自分が何と言うか、わかっていた。
「遠慮なんてしなくていいって」
しかし――何故そう言ったのかは、やはりわからなかった。
向かい合ったエレンとアニの距離はおおよそ3メートル。
半歩ふみ出せば、ひと跳ねで突きを打ち込める間合い。一歩ふみ出せば、身を沈めざまタックルに行ける間合い。
ライトコンタクトの取り決めではあったが――対峙する二人の空気は重い。
アニは前足を軽く浮かせ、後ろ足で立って両拳を頭の脇に構えている。左を前にしたオーソドックスの構えだ。
対してエレンは利き腕の右手を前にしかかとを浮かせてリズムを取っている。右利きのサウスポースタイルという攻撃的な構えだった。
おたがいゆっくり右に左に廻るうち、縮まる距離にあわせてアニも前傾気味の構えに移ってゆく。
立合いの緊張が先刻ふたりの胸を騒がせた何かを鎮めている。
小柄で軽量なアニに、エレンが圧力をかけて前に出てきた。慎重に図った摺り足が微妙な拍子と間を割る。
その一歩は出るか出ないか、回るか下がるか――お互いの思考の綾が交錯する絶妙のタイミングを盗んでいた。それはアニの意の虚をついた。
――エレン、やる!
思えば最初の「授業」よりもうだいぶ経っている。
相手の研鑽の成果にアニも瞠目したその瞬間、エレンの右手がぴくりと動く。一瞬のフェイントから、奥足の下段廻しがアニの左の内腿を叩いた。
「ぐっ!」
アニが思わず呻くほどの、早く重い見事なインロー。闇夜とはいえ、エレンの稽古の成果はアニに反応を許さなかった。
技はまだ粗いが、攻撃に重要なのはいつ何処で何処をどう打つかだ。そして敵の息の根を止めずにはおかない、あくなき攻撃精神。
そんな闘争の「髄」を、エレンは本能的に知っている。
それはアニの知らないエレンの幼時――ミカサとともに賊を手にかけたときから、エレンの裡に宿ったものだ。
だからエレンは下がらない。一度攻勢に回ると、あくまで獰猛に喰らいつく。
続いてリーチにも僅かに勝るエレンは、アニの突きが届かない絶好の間から鋭い右ジャブを放っていた。
その矢のような拳をアニは内側に身を沈ませて入身することでかろうじて躱していた――
同時にその眼にエレンの既にタメの効いた左拳をはっきり認識していた。膝も選択肢に入っているはずだ。
それを無効化するため、アニはエレンの胸に頭を押し当てるように組み付いていた。同時に踏み出されていたエレンの右足の膝裏を刈る。
残った足で地を蹴り、肩をつけて体重を預け、エレンの重心を崩して押しこむ――胴タックルが見事に決まった。
アニの身体がエレンの身体を芝生の上に押し倒した。
エレンの背を地につけた瞬間、アニの下半身は地を蹴ってエレンの足を飛び越えている。
もがくエレンの身体の左脇側部、腕や首への関節技や馬乗りを狙えるポジションを、アニはあっさり制していた。
相手の左腕を両足に挟みこみ、もう一方の腕の手首を掴んで動きを殺そうとする。
暴れるエレンの喉もとに下腕部を押し付けて呼吸を邪魔しながら、胸を合わせる――。
「うっ…」
エレンが呻いていた。そう、今まさに弾力のあるアニの足が腕に巻き付き、胸の上には何か柔らかいものが押し当てられているのだ。
およそ取っ組み合っているとは思えないような、なんとも言えない感覚。言うまでもない、アニの胸のふくらみの感覚だった。
普段見ている兵士の制服姿からではあるのか無いのかわからなかったし、べつにどうでもいい物だった。
それがどうやら確かに存在するということが実感できたが――力が出ない。
アニの胸だけではない。腕も、おなかも、内ももも、全てが柔らかい。少女のみずみずしい弾力が、エレンの身体の上に載っている。
アニの胸は波打っていた。
無心に攻防を応酬した立ち技の局面とは違って――流れでテイクダウンしたのだが――エレンの力が抜けていっている。
触れ合っている内もも、腕、そして胸にはっきりエレンの戸惑いを感じる。それは同時に自分の中にもあった。
アニの肉体が真綿に包んだワイヤーなら、エレンの肉体は生ゴムで覆った鉄板さながらだった。
質の違う鍛えられた肉の、その奥にある鼓動が布越しに伝わってくる――。
『ドキドキしちゃってるとか?』
先刻のミーナの台詞が唐突にアニの脳裏を打った。
――違う!
アニは否定の文言を浮かべながら、眼前のエレンの右腕を取りにゆく。
肘を押さえながら手首を取り、腕がらみを狙った。その意図はエレンも察していた。
萎えかける右腕に力を入れ、アニの手を手首から振り払おうとする。同時にアニの足に挟まれている左腕を引き抜こうと捻転させた。
アニの尻が僅かに跳ねた。もがくエレンの上腕部が、足の付根のあたりで暴れたのだ。
そこから背を駆け上った痺れにも似た妙な感覚に、アニのエレンの両腕に対するロックがゆるむ。
すかさずエレンは足で地を蹴り、身体を反りあげた。右手首からアニの手をほどくとその肩を押してはねのけようとする。
その手は体勢を変えようとしたアニの、まさに胸乳の上に押し付けられた。
布地の下にはっきりわかる、手の中の丸いやわらかいふくらみ。その下の大きな動悸がエレンの手のひらに伝わった。
「う…」
「あ」
予期せぬ接触に二人の時間が止まったかも知れない。
一瞬の停止から、アニはその胸に置かれたエレンの手首を取って腰を浮かせた。それを軸に低く素早く身体を一転させる。
両足の間にエレンの腕を挟みこみ、片足をその胸の上に投げ出し、一方をエレンの首に巻く。
両腕でエレンの手首を掴み取り、後ろに背を伸ばし――そのまま地に倒れこんでエレンの腕を伸ばしきれば、腕拉ぎ十字固めの完成となったが――。
さすがにエレンも反応した。
肩を起こしたエレンは伸ばした左手とアニに抱え込まれた右手でクラッチしていた。
浅くブリッジしながら、持って行かれそうになる右腕を必死で守る。伸ばされれば即、終わりだ。
アニはエレンの手首を掴む手をずらし、下腕の内側に深く抱え込んだ。内ももを締め、全身でエレンのクラッチを切ろうと力を込めようとした。
唐突に、アニは気づいた。
自分の足の間のエレンの上腕のこわばり。うねり。エレンの肘のあたりが、自分の胸のふくらみの間に挟み込まれている。
――熱い。
アニの頬に血がのぼっていた。それは力を込めているからだけではない、何か胸の底からやってくる温度。
――でも、不快じゃない。
膝の裏がふるえる。込めていたはずの力が、まるで溶けるように抜けかけた。
「おおおっ!」
エレンが低く吠えた。緩んだアニの肉体を押しやるようにブリッジし、下半身を反転させる。アニの体が後ろに転がった。
体勢が反転し、先ほどとは上下逆の体勢になった。
腕はいぜん逆さまになったアニに掴まれたままだったが、エレンは中腰で立つ。体重をかけて、腕十字の体勢を押しつぶすためだ。
首に巻き付いていたアニの足はずれている。三角絞めや再度の腕十字を警戒しながら、腕を体ごとアニの側に押し込もうとした。
上手くいけばサイドを取れるはず――。
ふわり。
何かかぐわしい空気が舞い上がり、エレンを包んだ。それはアニの汗の匂い。そして髪の香り。
取っ組み合っている真っ最中に、場違いな香りだった。
それはたちまちエレンを狼狽させた。
くらんだ視線の先に、アニと眼が合う。闇に青い目がうっすら光って――かすかに潤んでいるようにも見えた。
白磁の肌は夜目にもあらわに上気している。きっと自分も同じだろう。アニに触れた部分から、なんとも言えない感触が、腹の底に伝わってくる。
ふと、自分たちのとっている体勢の事が浮かんだ。腕を取り合う妙な体勢で身を絡めあい、息を荒らげている二人。見ようによっては滑稽だが――。
――こいつ、こんなに綺麗だったっけ。…畜生、なんでこんなに、ドキドキするんだよ!
もうやめだ、今日はもう寝る、そうエレンは叫びだしそうになった。
むしろエレンの端々の対応に舌を巻いている。
最初の訓練時の喧嘩屋然とした荒い動きから、闘争心はそのままに技術が着実に身についている。
それはアニの指導によるものも大きい。本当に真剣に戦ったら、今ではどうなるかちょっとわからない。
――私がエレンを強くした。
そんな想念がふっと浮かんだ。無駄だと思っていた自分の技が、他者の中で実を結びつつある――それは無駄で無意味なことなのだろうか?
そしてそれは――。
――嬉しい、かもしれない。
今までアニの中にはなかった感情だった。アニはそんな思考にたどり着いた自分に驚いた。
『アニがちょっと丸くなったの、…エレンのせいだったりする?』
ミーナの言葉が浮かんできた。やっぱり見ている者は見ているのだ。
アニはもう否定の言葉を浮かべることはできなかった。
「…やるようになったね、エレン」
そんな賛辞は照れ隠しか、自分への言い訳か――そのどちらでもあるのだろう。
「お…おかげさんでな…!感謝、してるぜ…」
エレンの返答もあるいは照れ隠しだったかも知れない。
だがアニはその声を聞いたとたん、顔が熱くなるのを止められなかった。
こらえかねたように、アニは弾けるように動いた。
下からの腕十字は捨て、体重を掛けるエレンの動きに乗って腕を引き、前にのめらせる。
同時にエレンの片足をたぐるようにその股下にもぐった。
アニは一瞬四つん這いになったエレンの足の間を潜りぬけ、瞬時に体を起こすとがら空きの背中に飛びかかった。
エレンが手をついて起き上がろうとしたときには、アニはその背後に密着していた。
バックポジション。アニの足がエレンの腰に絡みつき、腕がエレンの首に巻きついた。エレンはうつ伏せに地面に潰れてしまう。
エレンの背中一面にやわらかなアニの肉が押し付けられた。鍛えられた腹筋も、控えめなふくらみも――。
耳にアニの吐息がかかり、触れ合う髪から少女の香りがエレンの鼻孔に流れこんでくる。
うつぶせたエレンの身体の芯にかっと熱が生まれ、甘やかな痺れのようなものが広がっていく。
エレンの身体が緩んだその一瞬をアニは見逃さなかった。
アニの胸と腹が反り、エレンの上体を引き伸ばす。蛇のように首を制した腕が深く食い込んでゆく。
頸動脈を締め上げるそれは、完璧な裸絞めだった。
『ドキドキしちゃってるとか?』
アニの脳裏に、またその声がした。
――そうだな…ドキドキ、してるよ。
最初に見た時から、エレン・イェーガーと言う男は真っ直ぐで、必死で、ひたむきだった。
私とは違う。私は熱くなれない、こんなくだらない世界で。
だからかも知れない。だからこそ…気になった。
そうだ。ずっと気になっていた。
エレンが欲しいのは私の技術だけだ。それはわかっている。でも…。
上手く言えない。でも、これが…好きって事なのかもしれない。
アニは全身にエレンを感じていた。持てる力の全てでその首を締め上げる。
そう、獅子が獲物を仕留めるときのように。
もう逃げられない。
呻くこともできないエレンはアニの腕を力なくタップし、負けを認めた。
漆黒の闇の中、二人は草の上にひとかたまりになって転がっていた。
うつ伏せのエレンの首に腕を廻したまま、アニはその背にからだを預けていた。脚のロックは解かれ、エレンの脚の間に流れている。
密着した背と胸の間を互いの脈打つ鼓動の音が行ったり来たりしていた。
どのくらいそのままでいただろうか。
「お…おい…タップしただろ、…離れろよ」
エレンが腫れ物にさわるような、おずおずとした声をあげた。
「…」
アニは答えない。その沈黙が、エレンには重い。
同時に、甘い。もうエレンは自分の胸にかかった靄がなんなのかはっきりわかっていた。
アニの双眸によって。上気した白磁の肌によって。そのしなやかな筋肉の感触によって。汗のにおいによって。やわらかなふくらみによって。
いままで同期の仲間、格闘術の先達くらいにしか思っていなかったアニの、少女の部分によって――
エレンは欲情していたのだ。
彼がうつぶせから動かない、いや動けないのもそのせいだった。
自分の身体を持ち上げるほど――肉棒を充血させていたのだから。
アニはエレンの汗の匂いを呼吸していた。
自分の汗が温度が、エレンに染みこんでゆくのが心地良かった。
――自分はこの男を好きになっていたのだ。
身体の火照りは疼きに変わっていた。
「エレン」
自然に口が開いた。口を開いて言葉がどんな音を立てるのかわからなかったが、アニは語りだした。
「…あんたは私が必要?」
「な、何言ってんだよ…」
「答えて」
「そ、そりゃ…格闘術…教えてくれるし…仲間、だし…」
狼狽したエレンはアニの意図に考えが及ばない。
「私も…必要かもしれない」
アニの「必要」は、エレンのそれともちろん意味は違う。
一言ごとに自分が変わってゆく感覚が、アニを揺さぶっていた。
次に何を言うかも決めず口を開く。
「でも私は目標があって…それはあんたと同じ所を向いていない」
「あ、ああ…憲兵団に行くんだろ…?」
アニの目指す内地で王を守護する憲兵団は壁外で巨人と戦うことはない。
それは大抵の成績優秀者の目標であった。何故なら戦死の可能性から圧倒的に遠ざかることができるのだから。
彼女のその目標は、壁外で活動し時として巨人と戦わねばならない調査兵団を目指すエレンとは対極にあるのだった。
そして互いの目標は絶対に覆らない。
それは未来の暗示でもあった。訓練所を卒業すれば、一度別れて二度と合わない――そんな永訣の定めの。
その定めがわかっているから、いまアニの心は激しく動いているのかも知れない。
火照った身体と昂ぶった心が、ふだん冷静だったはずのアニの自制を吹き飛ばしていた。
「…一回だけ。今までの授業料、ってことで…あ、あんたを…好きにさせて」
顔じゅう真っ赤にして、アニはその台詞を吐ききった。闇夜の中、背中越しででもなければ最初の一文字も発音できなかっただろう。
「う…あ…?」
「いや、…する」
エレンはアニが何を言っているのか、音は拾っても意味には思いが及ばない。
考えがまとまる前に――アニの腕が首から離れ、地面と身体のあいだに潜り込んできた。
「な、おい、アニ!?」
「…遠慮なんて、しない」
エレンはあまりのことに身じろぎも出来ないが、白く冷たいアニの手の感触は熱くなった身体にここちよい。
白い手はエレンのへその下に無遠慮に侵入してくる。
片方がシャツの裾を引きぬきめくり上げ胸に這い登る。もう一方はためらいなく下に伸びた。
「そ、そこは、おい!アニっ」
アニの指先が肉棒に触れた。ズボンの上端でちょっぴり先端を覗かせ、苦しそうにしていたそれは柔らかいものにふれてぴくぴくと震えた。
たちまちエレンの腰が引ける――膝をわずかに立てて尻を持ち上げた形になった。
首筋にかかる少女の荒い吐息が、背中を押す柔肉の感触が、エレンの脳をあぶる。
「う…く…」
「興奮…してたんだ」
ささやくようなアニの声も、どこかうわずっている。
手の中の、初めて触れた異性の性器の反応に驚きと好奇心がないまぜになっていた。
食堂でたまに耳に入る同性異性のひそひそ話から仕込んだ乏しい知識を思い出しながら、好きになった男の体に触れたい衝動をありったけ発揮する。
まずは手を思い切り突っ込んで、手のひら全体で肉棒の形をさぐってみる。アニの手には余る大きさだ。
――…こんなに大きいのか?それに熱くて…脈打っていて…。
実のところエレンの肉棒は体格に比して少々大きめ程度のサイズで、単にアニの手が小さいための錯覚だったのだが―。
――私の身体が、エレンの、これ…をおおきく、した。
そんな事を考えたアニはますます昂ぶった。
以外に華奢な手指でその熱い幹をいっぱいに掴むと、するするとしごき始めた。
軽く浮いたエレンの腰が、ぶるぶるとふるえて跳ねた。
「うあっ!や、やめろ、アニ…っ」
呼吸だけを荒らげたアニは無言だ。草を掴んで快感に耐えるエレンの背のうねりが密着するアニの身体を揺らす。
アニはその背に体重を預けながら、胸を撫で回していた腕もエレンの下腹部に伸ばした。
手のひらで亀頭をくるむ。にじんでいたねっとりとした液体を手のひらに塗り広げ、肉竿をしごく動きにあわせてこねまわした。
湿った粘着くような音と手が布と擦れる音が、次第に激しくなっていく。
耳まで真っ赤にしたエレンは草に額を押し付けて耐えている。
「…エレン…気持ち…いいか?」
小刻みに息を吐くばかりのエレンの反応に、アニはぞくぞくとした。
――気持ち、いいんだ。こんなにぴくぴくして…エレン…可愛い―。
しごいて、撫でまわして、転がして――だらだらとよだれをたらす先端をくりくりとさすって――アニは思いつくままエレンの肉棒をもてあそんだ。
「あ、アニ、アニっ…!」
エレンのなにか切羽詰った声がした。アニはぴんと来る――エレンはもう達しそうなのだ、とすぐに理解した。
そう思うとアニも腹の底がきゅんきゅんと疼いてくる。自分がエレンを射精させる、そう考えたとたん体の奥が燃えるように熱くなった。
からだをさらにエレンに押し付け、エレンの裏ももに下腹部をこすりあわせたとき、それは来た。
アニの手の中のエレンの温度が上がり、ふくれあがった。
「う、くっ…ああぁっ!」
少年のくぐもった呻きと共にびしゃりと草に白濁液が叩きつけられた。
同時に、アニも手の中に二度三度とエレンの痙攣を感じながら、腰を震わせて達していたのだった。
エレンは放心状態だ。異性に後ろから抱きつかれ、そのまま手指で射精させられるなど当然人生で初めての事だった。
むきだしになった肉棒にはまだ少女の手が絡みつきゆっくり刺激を与えてくる。若さのせいもあるが、萎える気配はいっこうに無い。
エレンの背中に張り付いたアニは、何か赤子のおしめを替えてやった母親のような、そんな妙な心持ちを味わっていた。
同時にまだまだ物足りなかった。もっとエレンに触れたい――これが最後だから。
アニは身体を起こすと、エレンの肩と腰を引いてその身体をあお向けにひっくり返す。
ようやく闇に慣れたアニの眼にうっすらとエレンの肉棒が映った。まだ大きいままだ。
アニは今度は身体を横たえると、エレンの腰に頭を寄せた。根っこを掴んで肉棒を起こす。
吐息がかかるほど眼前で、アニはそれをまじまじと眺めた。
エレンはもうわけがわからなかった。
ただ自分が何か後ろめたいような後暗いようなことをしている、そんな気が一瞬頭をよぎったが、下腹部に与えられる刺激に思考を中断させられてしまう。
顔を起こすと、自分の肉棒越しにアニの眼が見えた。何をしようとしているのか、エレンがその意図を測りかねたとき、アニの頭が持ち上がった。
――まだ…熱い…変なにおい…エレンのにおい…。
アニは鼻を鳴らすと少しためらった後、濡れ光る肉棒の先端にくちづけていた。
「くぅっ!お、おい…」
射精直後の敏感な肉棒にやわらかなキスを捧げられて、エレンはたまらず呻いた。
それを聞くなり、アニは舌を差し伸ばす。亀頭の裏をそろそろと舐めまわし、吸い付いた。
何度も跡が付くほど強く吸いついて、舌の先でくすぐる。先端から垂れる残滓も迷わず舐めとりながら、エレンの顔を見つめた。
「うっ…」
エレンは思わず息を飲んだ。
普段は怖いほど張り詰めた凛としたアニの顔が、耳まで真っ赤にして瞳を潤ませている――それが、自分の肉棒の向こうに見えるのだ。
その濡れたくちびると赤い舌がうねるたび、頭が真っ白になりそうな快感がのぼってくる。
アニは霞がかかったようなエレンの顔を見て、少し得意な気分になった。
――感じてる、エレン。いつも必死な顔で訓練しているのに…。
エレンの反応から、アニはコツが分かってきた。肉棒の先端、亀頭の周辺が、エレンは気持ちいいらしい。
――ここが弱いんだ。だったら…。
アニはくちびるをひらくと、エレンの先端をぱっくりとくわえ込んでしまう。
「あ、アニっ!それはっ…」
エレンはたちまち情けない悲鳴をあげた。
舌が裏筋で暴れまわっていた。同時に吸いつきながら、アニはゆっくり頭を上下させ始める。
さすがに恥ずかしいのか、アニの瞳は閉じられている。
エレンはもう気が気ではない。
興奮と混乱で頭がどうにかなりそうになっている。草を掴んでいた手も宙をさまよっているような有様だった。
ふと視線を動かすと、頭が動くたびに小刻みにうねっているアニの腰のあたりが目についた。
上着の裾がめくれて、白い腹筋が覗いている。エレンはそこに手を突っ込んだ。
「ぷあっ…!エレン?」
驚くアニを無視して、エレンの手はアニのズボンの中をかきわける。
「エレン…や、やめ…ろ…」
アニは一応かぼそい抗議をしてみるが、もう自分もたまらなくなっていたところだ。
エレンが手を出さなければ自分で手を伸ばしていたかも知れない。恥ずかしさよりも嬉しさのほうが先にたった。
言葉とは裏腹に、アニは腰をエレンの方に僅かに寄せると閉じられていた膝を僅かに持ち上げていた。
エレンの手が、すぐに手触りの良い布地にあたる。それは下着だったが、両足の付け根の方を目指してその中に潜り込んだ。
すでにしっとりと湿ったそのあたりを、文字通り手探りで這い回る。
うすい茂みのようなものをかき分けると、指の腹になにかぷっくりした芽のようなものが当たった。
もっとも敏感な所をまさぐられて、アニが喉をならした。
――触っている。エレンが私に触っている。ぐちゃぐちゃになっている、私…。私がこんなになるなんて――。
エレンの手はアニの肉の芽をひとしきり転がすと、その下の割れ目に這いよってゆく。
ぷるぷるとした肉をかきわけて、すでに潤っている入口のあたりをこねまわした。
少年の手指の動きは利き腕ではないせいか荒っぽくぎこちない。それでもアニは気が遠くなりそうになった。
肉棒を咥えているため声こそ上げないが、まるで猫みたいに切なげに喉をならし、身をくねらせた。
「へ…なんて顔、してやがる…泣く子も黙るアニ姐さんが、よ…」
エレンの減らず口も語尾が震えている。恥じらうアニの顔に恐ろしいほどドキドキして、逆に肉棒に感じる官能が高まってしまう。
アニはその台詞に少しむっとしたのか、ちょっぴり歯を立てて口中の肉棒を甘噛みした。
――う…うるさい、そっちだって馬鹿みたいな顔になっているくせに――。
アニは心のなかでそう毒づくと、亀頭に強く吸いつくき先端に舌先をねじ込み暴れさせた。
「うぁっ!あぁっ…!」
エレンの脚がばたつき、草を蹴った。跳ねた草がそよぎ始めた夜風にのって散ってゆく。
少年の顔も少女の顔も、もうお互いが与え合う快感でとろけきっていた。
ずっとその快感を味わっていたいくせに、二人の絶頂へと必死に手指と舌を働かすその動きはまるで遅くならない。
もっと激しく、もっと気持よく――アニが吸い上げ、エレンが指を食い込ませた。
「あ、あああああっ!」
こらえかねたエレンの腰がはねあがった。
いきなり喉奥を突かれたアニは、反射的に肉棒をちゅぽんと吐き出していた。
同時に大きく脈打った肉棒から二度目とは思えない量の粘液がほとばしる――。
それはアニの頬に跳ね飛び、朱に染まった肌を白濁色に汚してゆく。
アニもエレンの温度を感じながら、腰を震わせてのぼりつめていった。
二人の荒い吐息が風にまぎれている。
アニは大の字のエレンの腿を枕に転がっていた。
口の端に垂れたエレンの絶頂のあかしを、赤い舌で舐めとった。
――変な味。でも…不思議な味。エレンの味。…もっと。もっとだ。もっと欲しい――。
アニは靴を蹴り出すように抛り出した。
横になったまま自分のズボンに手をかけ、ゆっくりと引き下ろしてゆく。自らの粘液で重く湿った部分が肌から離れ、風が白い尻肉をなでた。
驚いたエレンはがばりと上体を起こしていた。
「お、おいアニ!何してんだよ」
無視したアニは膝立つとエレンの腰をまたぎ、腿の上に座った。
エレンの肩に手を置いて、じっと見つめる。多少落ち着いてはいるが、いぜん白磁の肌は赤く染まったままだ。
濡れた瞳を向けられて、エレンはまた狼狽した。
あらわになったアニの白い脚がエレンの腰に当たっていた。そしてさっきエレンの指がかき回したアニの秘部が、反り返った肉棒の付け根に触れている。
「お…お前…」
「…」
無言のアニの手が下に伸びて、まだ勃ったままのエレンの肉棒をそっと掴んだ。
もうアニが何をしようとしているかは鈍いエレンにも明白だ。
エレンの額に汗が浮かんだ。
「い、いや、いやいやいや!こ、混乱つうか流されちまったけど!…こ、コレって…セックス…だよな。いいのかよ、お前」
「…さい」
アニの唇がわずかに動く。
「あ?」
「…うるさい。わ、私は好きにするって言っただろう。さっき、負けたくせに…言うとおりにしなよ」
言い訳がましいアニの顔は、まるで駄々をこねる子供のようだ。普段の氷のように落ち着いた印象はもうどこにもない。
あるいはこれが、彼女が抑えつけてきた「年頃の少女」の顔なのかも知れなかった。
「負けって…。…で、でもいいのかよ、普通こういうことは好きな奴と」
もごもごとそこまで言ったエレンの唇が、いきなり塞がれた。
アニのうす紅の唇が押し当てられていた。
眼をとじたアニの、何か必死な表情が、エレンの胸をついた。
「エレン」
唇を触れさせたまま、アニが名を呼んだ。それは自分の心を顧みるためのつぶやきだった。
――さっき授業料なんて言葉を使ったのも、照れ隠しの言い訳だ。詭弁だ。欺瞞なのだ。
本当は、…本当に本当の所はエレンの心も欲しい。
だが、どっちみちそれは手に入らない。どうせ望んでも無駄なものなのだ。
エレンにはミカサがいるし…それにこの男は調査兵団に進んで壁外に出る。
少なくとも巨人を殺すという目的、その一点だけはこの男の中では絶対に変わらない。
そしていつか、そう遠くない未来のいずれかの時点で死ぬだろう。
同じ時間は過ごせない。
だから、今。今しかないから――
アニは唇を離すと、濡れた声をエレンの唇に注ぎ込んだ。
「…今だけだから。今ぐらい…私のものになりなよ」
いつのまにか、風に流れた雲間から月光がもれていた。
漆黒の闇をほんのり薄く照らす明かりが、地上の人影を浮かび上がらせていた。
エレンの頭は真っ白になっている。
少女の言葉を聞いた時から、なにか物語の中にでも放りこまれたような、そんな心地になっていた。
アニはゆっくり膝立ちになった。
その手がエレンの肉棒を導いて、先端をみずからのやわらぎの入り口へあてがう。
そしてゆっくり、ゆっくり腰を降ろしていった。
初めての経験に引き伸ばされた時空感覚が、1ミリごとに襞をかきわけるエレンの肉棒の感触をアニの脳裏に刻みつけてゆく。
――入って来た。エレンの、これ。…私の中に。
熱い。熱い。熱い。熱い。エレンの温度。私のもの。今は、私のもの――。
アニの体の奥底で何かが開いてゆく。同時に、エレンに挿入されている側の自分が、何故かエレンの身体の中に沈み込んでゆくような感じもした。
エレンは先端にうっすらと抵抗を感じた。
それが何かもよくわからないまま、眼前のまぶたを閉じた少女の目尻に浮かんだ光る粒を、とても綺麗だと思って無心に見ていた。
抵抗は何かぷちん、という感覚と共に消え失せた。いつの間にか――膝を折ったアニがエレンを根本まで飲み込んで、腰の上に座っていた。
「…っは…あ…ぁ…エレンん…」
アニは呼吸するのも億劫そうにおとがいをそらしていた。
ひょっとしたらエレンを奥まで迎え入れて、軽く達してしまったのかも知れない。
切なげなその顔を見て、エレンは初めて、この少女を可愛いと思った。
同時に腹の底から吸い込まれてゆくような快感が駆け上ってきた。いままさに、自分は異性の体内に入っているのだと思いだした。
少女の手がそっと持ち上がる。
エレンの上着の裾を掻き上げると、そろりと腹から胸を撫で上げる。
「エレン…動く、よ…」
鎖骨の下でそれが止まると同時に――少女のからだが波打った。
膝を使って腰を持ち上げ――脱力したようにエレンの腰の上に尻を落下させる。
破瓜の余韻など、アニは一瞬で消化してしまったらしい。
その動きは貪欲にエレンを貪ろうとする昂ぶりそのものだった。
「うぉっ、い、いきなり、アニ!」
「エレン…熱い、よ…。熱くて…痺れ、る…!」
肉棒で自分の中をかきまわすようにアニは震えながら腰をひねくる。
鍛えられた体幹の肉が尻肉を自在に捻転させ、エレンの肉棒を食い締め、しぼりあげていた。
「ふぅっ…あぁっ…!んぅぅ…!」
アニの喘ぎは動いているせいもあるが、恥らいもあって押し殺すようだ。
「うぁ…アニ、やば…い…」
アニの汗が跳ね飛び、エレンの頬に当たる。
エレンは腰から下がまるで溶けてしまったような快感にさらされていた。
アニが上下するたび揺れるたび、肉棒がアニの奥へ吸い込まれそうになる。腹の底をしっかり締めておかないと、たちまち搾り取られてしまいそうだった。
一度だから。これっきりだから。
そんな自分に課した制約がむしろアニの欲情をあおっていた。
自分の腰のひとうねりごとにぴくぴく痙攣するエレンの反応がたまらない。
吹きこぼれる愛液がエレンの衣服に染みとなってもまるで気にしない。
むしろ乱れる己のさまをエレンに見せつけるようにただむちゃくちゃに腰を振りたくる。
アニはエレンの中に、この時間を刻みつけておきたかったのだった。
いずれやってくる訣別の時を過ぎても、そう、この男が息絶えるその時まで、自分の事を忘れないように、と。
「エレン…いいか…?私のなか、気持ちいいか…?」
「そ、そんなこと…」
いたずらを見つかった小僧みたいなエレンの表情が可愛かった。
アニは喘ぎながら、エレンの胸を爪を立てて掻きむしる。背中にも手を回し、爪を立てた。
「なんと言おうと、わかる。つながって、いるんだから。イイんだろ…?エレン…?」
無言でこくりとうなずいたエレンの動作がアニをさらに興奮させた。
エレンの上着の襟をはだけるとあらわになった首筋にむしゃぶりつく。エレンの汗の匂いをかぎながら、歯を立て甘噛みし、吸い付いた。
いっとき自分のものになった男に自分のしるしを残しておく、それはマーキングだった。
「うおっ」
エレンは下腹から湧き上がる快感に意識が飛びそうになっていたが、首筋の痛みで我に返る。
そしてその痛みすら、じんわりと甘い官能に変わってくるのが不思議だった。
エレンに抱きついたアニはさすがに疲れたのか、腰を押し付けてうねらせるだけになっていた。
――もっと。エレン、もっと。
少年の背に立てた爪を食い込ませ、血が出るほど抱きしめる。
「…エレン、動いて」
アニはエレンの耳元でささやいた。そしてゆっくり膝を立て、脚を持ち上げるとエレンの腰の後ろで組み合わせた。
先程の立合いでそれを感じなかったのはアニの持っている技術とそれからくる畏怖めいた感覚もあったのだろう。
肉と肉をつなげた今では、アニのからだはさほど体格に恵まれていないエレンよりさらに小柄な、やわらかくてあたたかい「女の子」と感じられる――。
「…うごいて」
その「女の子」が、もう一度同じ言葉をあげた。そのとたん、エレンの胸に何かが燃え上がった。
犯したい。貫きたい。気持よくしてあげたい。気持ちよくなって欲しい――征服欲と献身がないまぜになった、それは奇妙な感覚だった。
エレンはアニを抱きつかせたまま前に押し倒した。
草の上に背を押し付ける。
エレンはそのまま腰を思い切り引くと、アニの奥底へ思い切り突き込んだ。
入り口のきつさも、その奥の広がりと襞の変化も、そして最奥の門のすぼまりも――全てが初めてで、新鮮な快感だった。
何度も何度も、それを繰り返すうち――
「ふぁあっ!」
アニのくちびるから、聞いたこともない声が上がった。エレンは耳を疑った。
思わず顔を上げ、アニの表情を覗き込む。アニは真っ赤になって眼を伏せた。
「ばか。…なんだよ…み、見るなよ…」
同時に奥底へ引きこむかのように肉棒をつつむ襞がぞわりとうねる。
それがあまりに気持ち良くて、エレンはたまらずそのまま腰をぐるぐるとねじこんでゆく。たちまち悲鳴のような喘ぎが上がった。
「あぁぁあああっ…あばれ、てる…エレン、が…」
間違え用もないアニの声が、もう濡れて溶け落ちそうになっていた。威のこもった兵士の面影はもう見当たらない。
「エレン、それ、いいから…もっと…もっと…!」
「くそ…アニっ…!なんでお前、こんなに可愛いんだよ…!」
エレンはいわれるままアニの奥底をかきまわしてやる。
背中をまた引っかかれたようだが、そんな事はお構いなしだ。
今はミカサのこともアルミンのことも、巨人のことも忘れていた――そう、今だけは。
アニは解放されていた――獅子の心を持つ、兵士の自分から。父の残影に苦しむ、影のある少女の自分から。
他者を容れず交わらない、孤高の個人としての自分から。
アニの純粋な感情がエレンに入っていって、もう境目がわからない。
たぶん、エレンが感じている快感を官能を、アニも同じく味わっていた。
大きな波の上で、剥き出しの二人が揺れている。
そんな中、終りが近いという予感が、身を絡める二人の動きを激しくした。
エレンの腰が動く。アニの入り口をこねまわし、肉の芽の裏側を突き上げ、半ばほどのあたりを左右にえぐり――
エレンの一動作ごとに、すすりなくような切なげな嬌声がアニのくちびるから漏れでた。
アニは身をよじり喉をふるわせ、闇夜に憚りもなく喘ぎをひびかせる。
――いっぱい。私の中、エレンでいっぱいだ。…もう気が遠くなりそう。…力が入らない――
望んでも求めても、もっともっとと渇いていたアニの何かが、いっぱいに満たされつつあった。
同時に消えかかる意識が、絶頂への予感を知らせていた。
そしてそれはエレンも同じだった。出すものがある男のほうがそれは切実だったかもしれない。
いつの間にか限界はすぐそこに近づいていたのだ。
「アニ、俺…もう…」
「…いい…よ…このまま」
アニはそう言うと、脚をしっかり組んでエレンの腰をロックしていた。
「おい、おまっ…!」
くすり。一瞬の抗議をやわらかく笑うと、アニは少年の耳にそっとささやいた。そう、幾度もこの男に投げかけた言葉を――。
「…遠慮なんて…しなくていい…から…」
「…っ!あ、アニっ…!」
その刹那、エレンの身体がひきつった。
低い呻きと共に、アニの奥底にエレンの精が叩きつけられる。
二度、三度、長い長い射精の脈動がアニの脳髄を灼き、闇を真っ白にそめあげてゆく。
心臓の鼓動だけが白い闇に満ちていった。
…心臓には人の心が宿るという。その一刻に、アニは己の獅子の心臓に宿った心を解き放っていた。
「エレン…あんたが、好き…」
たぶん一生で二度と無い、まごころを――「心臓を捧げた」瞬間だった。
アニはエレンの背を抱きしめたまま、そっと眼を閉じていった。涙がひと粒、草の葉に跳ねて散った。
エレンはその後アニと何度か顔を合わせたが、彼女はいつもと別段変わりもないように見えた。
いつものごとく冷静で、冷淡で、刃のような眼をしている。
あの一夜の交わりは、まるで夢か幻だったかのようだった。
エレンの方は大変だった。気がついたらアニは消えていたし、兵舎に戻ったら戻ったで汗と草と土にまみれた格好は目立った。
ズボンの股ぐらのあたりにはうっすら血のようなものも付着していた。
風呂に入れば何箇所ものひっかき傷に湯がしみる。それになにより首筋のアニの噛み跡を隠すのに一苦労だったのだ。
ライナーやアルミンに突っ込まれたら、そしてそれがミカサに伝わったとしたら?
何が起きるか想像もできないし、したくもない――。
エレンは戦々恐々として日を重ねていたのだった。
今日は訓練課程の終了を控えた能力評価試験の初日に当たっていた。
数日にわたって続くこの試験で評価された上位10名までが、卒業後兵科を選択するさいに憲兵団を選択することができる特権が与えられる。
巨人の殲滅や帰郷を志すエレンやライナーなどの若干の異端者をのぞき、
アニやその他同期の仲間達は内地に行ける憲兵団入りを目標に厳しい訓練に耐えてきたのだ。
初日は午前に座学の数科目と、午後から対人格闘術の試験となっていた。
午後、対人格闘術の試験。
訓練兵は何人かづつグループ分けされ、そのグループ内で総当りで試合を行う。
その試合を、眼を光らせる試験官――教官が審判し、評価をつけるのだ。
試験は訓練をしていた広場と同じ芝生の上で行われた。
エレンはライナーやベルトルトなど、強豪が揃ったグループで勝利を重ねた。
身体が軽くしなやかに動き、技はその局面で必要なものが適切に繰り出される。
体格に勝る相手には打撃に付き合わず、引きこんでの寝技で末端を極めあるいは締める。
同程度の体格の相手は打撃で圧倒した。
エレンはこの対人格闘術の試験評価で全訓練兵で2位の評価を受けることになる。
受け止めたエレンの視線の先には、アニが立っていた。
「お疲れ」
「あ、ああ…」
革袋の水がちゃぷんと音を立てた。エレンの首筋に血が上る。まともにアニの顔を見ることが出来ない。
脳裏には先日、闇夜に明滅した白磁の肢体がちらついている。
アニの表情はだから、エレンにはよく見えなかった。
「…何?」
しかしアニの方はというと、どうやら普段と変りない。
エレンは気をとりなおして顔を上げると、何とか会話をつなごうとした。
「い、いや…まぁ…。見てたんだろ?…ど、どうだ?俺の蹴り技は」
――どうせいつものようにダメ出しがくるんだろうけどな。
エレンがそう思ったとき、アニはうっすら微笑んだ。
そう、それは見間違えようもない、確かに笑顔だった。
「…まあ、いいんじゃない?」
「…あ?…え?!」
振り返って行ってしまった少女を見て、エレンは絶句したままその背を見送っていた。
芝を踏んでゆくアニのそばに、ミーナが寄ってきた。
「アニは試合、これからでしょ?」
「ええ」
ミーナのお下げがぴょこんと跳ねる。
「アニ、何か機嫌いい?…んー、またちょっと変わった?」
ぴたり、アニは歩みをとめた。微かに口の端をほころばせる。
「おかげさまで」
それだけ言うと、またすたすたと歩き出してゆく。
一瞬きょとんとしたミーナは、友人の言葉を反芻すると、思わず声を上げていた。
「…ん?えっ!えええええ?!」
試合の場へ歩んでいくアニの背中が、それを聞いてまるで含み笑いをするようにちいさく揺れた。
このときは誰もが、未来を疑わずに笑っていられた。
エレンもアニも、誰であろうとも、この試験の終了からほんの幾日か後に起こることを、いまだ当然知る由もない。
運命は運んでくる。大きな絶望と幾多の死と、そして小さな希望を――。
そう、これから始まる物語を――まだ誰も、知らない。
『獅子ノ乙女宵闇情歌』(ししのおとめよやみのこいうた) 了
補足 ミーナ・カロライナについて
あくまで念のためですが、ミーナはオリジナルキャラではありません。
原作一巻でエレンの班にいた黒髪お下げの女の子です。巨人に頭からかじられて死んじゃったあの子です。
名前は二巻でアルミンがミカサに対してエレン班の戦死を告げる台詞から、女の子の名前っぽいのはミーナしかなかったのでこの名前と確認。
アニと仲良しなのは、原作四巻の過去回想でエレンが「技術を駆使してこの場を収める」シーンでアニの向かい側に座っているのを確認。
また四巻で戦後処理の戦場清掃中にアニがミーナと思しい死体にごめんなさいしていることから仲が良かっただろうと判断したものです。
ミーナの口調や性格付けに関しては一巻からだけでは情報が少ないので、捏造しました。
あとがき
アニは父親がらみでもっと重くも出来たのですが、原作に父親の生死その他の情報がないので書きませんでした。
(自分としてはアニは生き方の相違から父親を徒手の決闘で殺害している可能性も疑っています。教官も儀礼通過済みと判断してますし)
クリスタも好きなのでネタがあれば書きたいのですが、なにぶん原作の情報が少ないもので掘り下げできないのが辛いところです。
では長々と失礼しました。読んでくださった方、ありがとうございました。
アニへの愛を感じる
…クソッタレもう来やがった!立体起動に移れッ!!
ありがとう
やめろ!
原作準拠だとしてもこの御仁に兵長は低くね?
俺なら大佐相当の働きだと思う
「なっ!? ID:XNOPbS1i司令!?」
ってことか
「【進撃の巨人エロSS】エレンに対人格闘術を教えていたアニが、今までの授業料としてエレンに要求したものは・・・」終わり
なんかおもろいやつやらなんやら
な、なんやこれ?
「進撃の巨人」カテゴリの記事
最新記事
過去記事ランダム
この記事を読んだ人へおすすめ
最新記事
過去記事ランダム
名無しくんのそのまんまが出たぐっちょぐちょのコメント書いてけよ!
今週、もっとも多く読まれたアブな記事
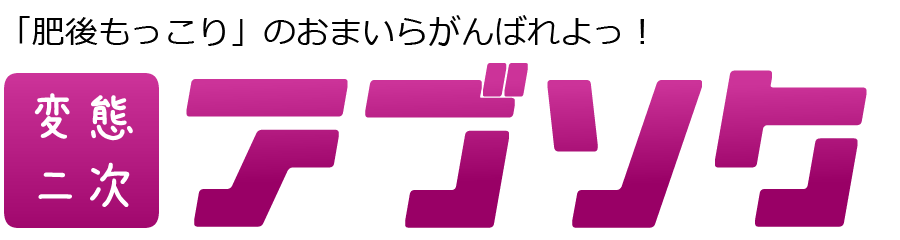




























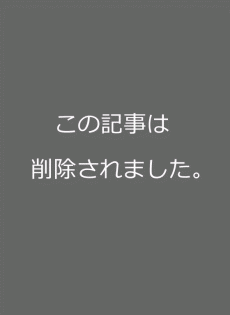
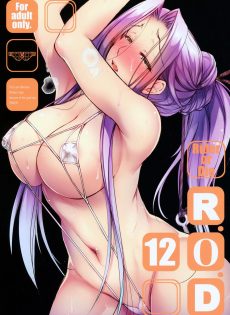





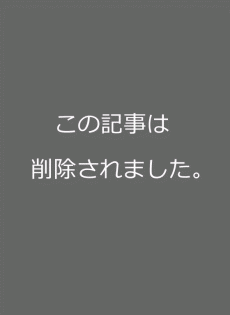


名無しくんのそのまんまが出たぐっちょぐちょのコメント書いてけよ!